|
|
No15
1990年7月4日発行 |
発見とは 無意識と意識化
1990年6月21日新潟県立小出高等学校で「高教研"美術・工芸"全県研究会」が開かれていて、私は、そこで「モヤシ」の授業をしていた。 約60名の高校の先生達が生徒である。
「モヤシ」は何のために描くのかを話をして、根っこ、くき、まめ、葉と描き方の説明をしていった。描き方の説明とは、そのものがどうなっているかの説明と同じである。
「葉っぱとは葉脈があって、まん中に一本通っていて、左右、斜め上に広がる。そして、そのような葉脈の葉は、双子葉植物といって、必ず双葉で出るんです」
私は、なめらかに説明する。
「スズランとか露草の葉は、葉脈が横に広がっていなくて、一点に集中します。これは単子葉植物といって、一つ葉ででます」
自分では確かめたことはないはずなのに、私の頭の中には、モヤシは双葉の芽がでるイメージがはっきり浮かぶ。
誰かが教えてくれて、「なるほど」と感心し、自分のものにしてしまったのだ。
「モヤシの双葉は、まず一枚の葉がまん中に通っている葉脈を中心に、半分に析れていて、こんなふうに重なっていまして、従って、まずは真ん中の葉脈から描いて」と説明した。
突然、後ろの方の席の女性から呼ばれた。「は−い」私は急いでその方の席へ行く。
「私のモヤシの葉、こうでも(A )なく、こうでも(B )なくて(Cの図)のようになっているような気がします。私のだけ特別かもしれません」
「えっ」私は驚いて「ちょっと調べるわね」と自分の席に戻り、モヤシの葉をとりあげ点検してみた。やはり二枚の葉は交互に接合されている。
「やっばりそうですよ。あなたの言うように双葉は交互に重なっています。知らなかったわ−」と興奮した。
「今まで、モヤシの授業を10年以上やってきて、知らなかったわ。今日、あなた大発見したのね。お名前は?」
「いいえ、結構です」と彼女は手をふり、ことわった。
私は久々に興審しまくった。なぜ10年以上も、こんなことに気づかなかったのか。
「スゴイ、スゴイ。モヤシの葉はこんなふうに重なっていたのか」
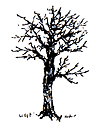
○ねえ知ってる?
1990年夏、私はモヤシの双葉のつき方を発見し、その後出会う人に興響してしゃべる。
宇都官の永田ひろ子さんに会うや 「永田さん、モヤシの葉ってこう重なっているの知ってた?」私は手帳を破り、二枚の葉の形にちぎり、双葉の組合せをした。
「うん、そうよ。一郎先生がいつもそうしてるわ。あれっ先生は今までどうしていたの?」
「エッ!」 東京に戻り、我が事務所の川合京子に
「ねえ、モヤシの葉のつき方はこうなってたの知ってる?」
「えっ私そうしていたような気がするけど・・・」と京子。
「一郎は知ってたみたいよ」と私。
一郎はニコニコしていたが、ニコニコしている場合じゃない。自分が発見したことの偉大さを知らなすぎる。
○偉大なことなのだ
キミ子方式は私が考えたもののように、本に書いたり、講演したりしているが、実は、こんなふうに無名のたくさんの人が考えたことを、私が文章にしてまとめただけ。
そのことに気づいたのは、イリオモテヤマネコの発見にまつわる話を、沖縄の親祖父さんに聞いた時である。 「一つのことを発見しても、それを発見したと自覚し、しつこくこだわり、それが意味あることだと考え、文字に残し、その考えを意識的に普及させなければ、考えたこと、発見したことにならない」
気づくことと、発見したことは遵うのだ。
キミ子方式は、産休補助教員をしている時に出会った、小中学生や、講演先で出会った、名前すら記憶することもない先生達がなにげなくする手付き、無意識に発する言葉を、私が、「それは偉大なことなのだ」と気づき、記録したのである。
「三原色で描く」とか「部分から全体へ描く」とか「画用紙が足りなければ足し、あまれば切る」ということを、多分、私以外の多くの人が実践していただろう。
「キミ子方式はオリジナルな考えではない。昔からどこかで誰かがやってきたことだ」と批判する人がいる。私はその批判には徹底的に反論する。なぜなら、そのこと(キミ子方式の特徴)が偉大であり、それでなければならないと気づいたのが、私の発見なのだから。
モヤシの葉のつき方の発見もそれを象徴している。
