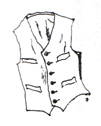|
|
No36 |
鳥取風景 -バカ正直・非常識-
五十八才まで必ず生きてられそう、と勝手に決めていた。母が五十八才まで生きたからだ。
<このままの人生でいいのかなぁ、自分の信じるものにこだわった方が・・・>と迷っていた三十代後半も、四十才になった時にパーンとはじけた。 あと十八年しかない人生なのだからと。
なにもいらない 新しく生き直したいと決めたときに、過去を全部捨てられるかと自分に問いかけた。
何もいらない。
ただ、自分の教えた生徒の絵、それらは私の家のタンスにぎっしり入っている。それらは私の考えた絵の描き方の証明書のようなものだ。だから、それだけは持ち出したい。あとは何もいらない。そう決心して、多摩川を歩いていたら、ふと足元に草花が咲いている。
ふいに、涙がハラハラと流れて、しゃがみこんでしまった。草花は、毎年同じ場所で、けなげに生きているのに、私はここから逃げようとしている。
多摩川べりに住んで十五年。三人の子供を産み、たくさんの友達に会えた。 真っ暗な深夜の恐怖から、祈るようにして待った夜明けを知らせてくれるのは、多摩川の上に広がる東の空。広い空と、広い多摩川が、日中の健さを守り、夕暮れの寂しさを知らせてくれたのだ。いつだって、北海道の広さに似ている多摩川の風景を眺めながら自分を確かめてきた。この風景と別れたくないと、草花をなでまわしてしまう。
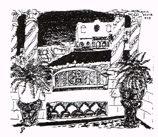

『バカ正直』?『非常識』?
『方法を変えれば、誰でも絵が描ける』と気がついて、たくさんの生徒達に実験してもらった。家出して二年、一九八二年に『本』になった。あちこちに講演にいくたびに聞かれる『どうして、そんなことを考えついたの?小さい頃から変わった人だったの?』そう聞かれて突然、思い出したのは母のことだ。母は鳥取の生まれであるが、私は一度も鳥取に行ったことがなかった。私だけでなく、私の兄弟もだ。北海道開拓三代目の私は、祖父母が故郷を捨てるのはそれなりの理由があるからで、過去を捨てられる人であるのを知っている。
幼い頃の事で、はっきり思い出す風景がある。母の膝枕のあたたかさと共に蘇る。小学校入学が私にとってはじめての社会参加だった。それまでは山の中で、家族として出会っていないからだ。
私は日本語を話したはずだった。ところが友達は何故か怒って行ってしまう。訳がわからなくて、淋しくて、学校から帰ると母に訴える。母の膝元で。母は『あなたの考えが正しいです。お友達は残念ながら心の狭い人なのです。あなたはそのお友達のように、心の狭い人にならないように』静かに話してくれた。
今思うと、母も変人だった。『不器用』『バカ正直』『非常識』と、かげ口をいわれていた。 きっと建て前と本音を使いわけられない人だったのだ。私も「建て前と本音」という言葉を知ったのは三十三才の時だった。二十才の若い女性が教えてくれたのだ。その時感動して私は言った。
「一体、そんなすごいこと、誰が教えてくれたの?」
私にも未来がある
八年続いた産休補助教員をやめた私は、私の考えた絵の描き方の実験場として美術学校をつくりたかった。誰だって絵が描けるのだから。年齢は関係ない。週三日くらい、時間も三時間くらいで。
今年は三期生が卒業する。
十代から六十代まで、十人程だ。
卒業制作展の会場で、十代のAさんは母子づれの参観者に語りつづける。
「わたし、ここに来るまで、自分に未来ってないと思っていたの。結婚するしかないなぁって。
でもまだはやいしなぁ、それ意外何も考えられなくて、とにかく未来とか希望とか、自分には関係ないと思っていたの。でも一年ここに来て、絵を描いて、自分にも未来があるって、わかったんです。なんでも出来るんじゃないかって」Aさんは四月からNHK学園の高校生だ。
一期生、二期生合計十四人の卒業生のうち、二人は美大卒だった。そして四人は美大生になった。その中のBさんは、私の前にお母さんがつれて来た時は、やせ細って、下を向いているだけの少女だった。
「キミコセンセイ、タスケテ、ママガイジメル!」と突然、幼児言葉で電話がかかってきたりした。
半年後は美大生になり、健康そのものに太った。上野での野外彫刻展に入選し、ボーイフレンドもでき、はりきっている。学校などの組織からはみでる人って、自分の気持にバカ正直だからではないか。その正直な自分に自信がもてる絵の描き方を見つけられて、本当によかった。・・・
「バカ正直」とかげ口を言われていた母に教えたかったが、母はもういない。せめて母の生まれたところの風景を眺めたかった。
鳥取という文字を見るだけで母とダブッてしまう。鳥取から来ましたと言う人に会うと、この人は母が見た風景と同じ風景を見ているんだと想い親しみがわく。
家出して十年目、五十才の時に鳥取行きが実現した。中学の理科の先生、川原三紀子さんが呼んでくださった。
その会場に、まるで私の母のように、情熱の固まり、建て前と本音がつかいわけられない主婦の小谷佳子さんが参加された。
その小谷さんがキミ子方式の全国大会に参加したいと常々言っていた。「幼い子どもがいるし、遠方までいけないので残念。いつか鳥取でやれたら・・・」という思いが実現し、一九九二年の第十回全国大会は鳥取で行われることになった。
鳥取は、おだやかな気候風土のところだ。日本一のトイレのある倉吉。そのトイレの近くに、椿の公園がある。公園のはしっこに「あぜくら」ー命の修繕屋ーという、予約客しか入れない食べ物屋がある。徹底的に自然食しか出さない哲学をもっている。
小谷さん、里美さん姉妹、陽さん達と、全国大会の下準備打ち合わ会のために「あぜくら」ー命の修繕屋ーのドアをあけた。
「おせわになりまーす」と私たち。
「ハーイおせわします」とご主人。
ここにも、母と似た匂いに出会った気がした。