|
|
No49 |
絵 10年たちました
〔絵・10年たちました大町登喜展〕の案内状がきた。
とっさに、私はもうすぐ53才。大町登喜さんに出会ったのは43才だったのか、と自分の年齢を計算してしまった。
ハガキの裏には、パステルで描かれた、クッションにうつぷせになった裸婦像だ。スゴイ。
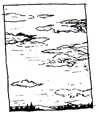
10年前は、丁度『絵のかけない子は私の教師』(仮説杜)と『三原色の絵の具箱』(ほるぷ出版)が出版された年だ。
本が出版されるや、あちこちの公民館から「夏休みの親子お絵描き教室」に指導しに来てほしいと言われた。
藤沢市辻堂公民館からの依頼も、それだった。二日か三日連続で、夏休みの宿題をこなせたらという母子の願いもあったようだ。
その講座の二日目に、一人の元気のない中学生がやってきた。その日は海を描く日だった。
彼は八つ切の画用紙を大事そうに、クルクルに小さく丸めて、輪ゴムをして持って来た。画用紙は、公民館で四つ切欠のを用意しているはずだ。
「この大きい画用紙に、大筆で思いっきり空を描いて、その下に小さく海を描こうよ」と行ったら、彼は困った顔をしてモジモシしている。
〈大きな画用紙だと、学校の宿題として提出できないよ〉と言いたいのだ。
それはわかっているけれど、学校の宿題用の小さい画用紙の中に描くと、空の広さも、空に比べて海が小さいもの絵を描いて味わえないよ。絵を描くことって、空になりきる。
海になりきる。描くものになりきる快感なんだから、画用紙の大きさって、とっても大事なんだ。
彼は私に反論する元気もなく、ただ、輪ゴムをとった八つ切欠のまるまった画用紙をひきのばそうと下を向いているだけだ。
「ねえ、若者。まずは、この大きな紙に描いてざ、絵が描き終わったら、学校提出用の、その大きさに切っちゃえばいいじゃない」と言うと、やっと彼は納得し、公民館が用意した画用紙に空を午前中に描き、午後は海を描いた。
炎天下の公園も、海からの風が涼しかった。
私は真夏に描く、海の絵が大好きだ。
ところで、少年の絵を学校提出用に切らねばならない。
「さあ、学校提出用の大きさに切りましょう」と彼に近づいたら「いいです」と、彼はきっぱりと私を見つめて言った。「どうして?この大きさだと規定の大きさでないので提出できないのに・・ことあせる私に、彼は「もったいなくて、切るなんてとんでもない」と、惚れ惚れと自分の絵を見つめてつぷやいた。朝、会った時と別人のように、ガッチリ意志と信念のある人に変身していた。
こんな楽しい出会いもあったけれど、多ぐは、幼児や小学校低学年の子と、その母親だ。
若い母親の、小さいうちにやっとかなくちや、大人になったら取り返しがつかないんじやないかという恐怖がエネルギーの、幼児虐待とさえ、感じられる親と子は痛々しく、苦手である。
私は公民館の館長に訴えた。
「私の考える絵の描き方は、幼児や小学校低学年用だけのお絵描きではなく、幼児からやったほうがいいというものでもなく、どんな年齢になってからでも、過去は間わず、絵を描くことを楽しめる方法なのです。できれば年筆の人に教えたい。私の母に絵を描くのを教えたかったのだけど、母はもういないんです。母にかわる人に教えてみたいんですが、そんな講座ありませんか?」
「シルバー教室はあるのですが、実は内容で困っていたのです。日本の文化は男文化と女文化に分かれているのです。お花やお茶は女。碁や将棋、世界情勢などは男という具合にね。せっかく、この世は男と女しかいなくて、男女一緒に学んでいただき
たいのにと思っていたんです。
「絵はいいですね、男と女が一緒に学べますものね」と館長は私の考えに賛同してくれた。


こんなきっかけで、シルバー講座で絵を教えられることになった。
その時、定年退職したので、長年の募である絵の勉強を始めたいという美しい方に出会った。大町登喜さんだ。
大町さんは、これからは近所の人と仲良く幕らしていきたいと、近所の人と集まって、三原色のキミ子方式の絵を描き始める。その時の文を『たのしい授業』No36「この世と別れるまで絵を描いていたい」(仮説社)に寄せてくれた。
「長く夫婦仲が悪かった奥さんが三原色の絵を描きはじめ、それを旦那さんが喜んで、はじめてプレゼントしてくれた。それが12色の絵の具で、うれしいんだけど困った」という話や
「絵が描けたら、亡き主人の仏壇のある部屋に飾って、見てもらいたくてギャラリーのように絵がいっぱいになっている」など、たのしいエピソードいっぱいだった。
登喜さんのお父さんが、老衰で床に伏した時「絵を見せに言っている話」も心をうった。「今の老人病院はひどい。ただ機械で延命させるだけなんです」と何かの析り、電話で悲しがっていた。
彼女は、せっかく定年退職されたのに、教育委員になられたとかで、又いそがしいようだ。
六年ほど前、私の三男が、中学三年の時、学校の廊下を走って、全面ガラスにつっこみ、両手首を切るという大怪我をした。
そのことを知った登喜さんは、お見舞い金をくださった。その時に登喜さんのお壊さんも、大学の研究所の事故で、瀕死の大火傷をしたことを知った。その時の世間の目の残酷さと、やさしさを知ったと話してくれた。
時々、絵はがきをいただいていた。御自分で描かれた絵もあった。一本の草花からはなれて、デッサンをして色をぬるという描き方に変わっていた。
「入門の時に出会ったキミ子方式が役立っている」と言う。確かに、素人とは思えない、しっかりした登山靴の絵があった。静物画の絵はがきの時もあった。あれから10年たった。
ハガキに同封された手紙には、この10年の中から、選んだ作品を並べますとあった。
少しやせられたかな、少しお疲れかなと私は見たが、彼女も私のことを、10年前と比較して見ているに違いない。
パステル画に描かれている女性の裸の色っぽさや衣類のシワの美しさは、登喜さんの特徴だと思う。
しかし、私は、親子二羽のカラスを描いた絵が好きだった。
「剥製のカラスを見て一羽描いてもう一羽を小さく描いて、子ガラスにしたのですが、カラスって、小さい頃は人の前に出てこないのですってね。だから、小さいカラスというのは、ウソなんですって。教えて下さった人がいたのよ」という話からはじまって
「事故にあった娘は、今ドイツの大学で研究しています。日本より障害者に対して偏見もなく、女性という偏見もなく、研究の中身だけで評価されるって、いごごちがいいようです」と娘の話から、お母さんの話になった。
「自宅で亡くなったの。私ず−っと見ていたんです。もう、何を言ってもわからないかなと主っていたんだけど、寝ている母の身体を撫でながらね「お母さん、もし、もう一度生まれ変わっても、又、お母さんの子どもにしてね」と言ったのね。そうしたら、その瞬間、母は顔がぽーっと赤くなって、はずかしそうな、うれしそうな表情になったの。そして亡くなったの。私、親孝行出来たような気がするの」
私は思わず涙した。いい話だった。
絵を教えることを通して、こんなにすてきな人に出会える。これが私の財産だと思う。