|
|
No51 |
なぜ 絵を教えるの?
チリの映画。イグナシオ・アグエロ監督作「一○○人の子供たちが列車を待っている」(一九八七年)を見た。
この不思議な題名は、一八九五年12月28日に、リュミエール兄弟が初めて映画を上映した、その世界最初の映画「列車の到着」からきているようだ。
サンチャゴ市内のポブシオン(大衆民住区)の一つ、ロ・エルミーダの質素な教会で、アリシア・ベガという五十代(?)の女性が、映画館に行ったことのない子ども達に、映画教室を開く。そのドキュメントだ。

子ども違は、靴みがきをして服や文房具やスニーカーを買う。ダンボール捨いで稼いでノートを買う貧しい暮らし。読み書きも教会で習っている。
毎週土曜日、午前十時に、様々な年齢の子ども達が教会に集まってくる。その子ども達に、映画作りの理論と、技術の初歩、野外の撮影方法、映画の歴史を教える。教室の終わりは"デモ"の映画(アニメ)を作る。
そしてラストは、オンポロバスに乗り、大人たちに見送られ、映画館のある街へ、ホンモノの映画を見に行く。期待と興奮。スクリーンを見つめる子ども達の真剣な表情。
この映画のはじめの方で、アクエロ監督(アリシアに、大学で学んでいる)が、アリシアに尊敬をこめてとろけるようにやさしい声で間く。
「アリシア、この子どもたちに教室を開いている訳は?」 「この子たちは今、国中で一番辛い目にあっていると思うから。物質的にも、精神的にも恵まれていないわ。私は教会の映画部門の代表として、五年間、私立や公立の学校で子ども達を教えたわ。公立学校に通う子はとても不利なの。経済的理由で映画にも行けない。だから、創造性を発揮する機会がない」とアリシアは語る。
創造するとは、物を見る目を育てることであり、考える力がつき、自分を発見することなら、銀幕の中の子ども達は、確実にそうなっていく
久しぶりにスペイン語を聞いて、一昨年メキシコに行った日々を思い出した。
クエルナバカに下宿して、近所の語学学校に通う日々。クリスマスイブにフト思い立って、タスコに行きたくなった。
タスコは『絵を描く子どもたち』(岩波新書)の著書もある、美術教育の大先輩、北川民治(一八九四〜?)氏が、六十年前、五年間美術学校を開いていた街だ。
クリスマスのせいで、満員の立ちんぼの三等バスしかとれない。乗客同志でカンパしてジュークボックスの音楽をガンガン鳴らし、さながらバスの音楽堂よろしく、四時間程かけて夕暮れのタスコについた。
サンタプリスカ教会が、街の真ん中丘の上にデーンと立っている。すぐ近くのホテル"メレンダ"に泊まる。冬なのに、シャワーは水しか出ない、古い、わびしいホテルである。
その夜、サンタプリスカ教会の前で、五才から二十才くらいまでの子ども達による野外劇が演じられた。
劇に出演する子ども達は裕福そうな、教育パパママの大声緩で、舞台に出る。その劇を、観光客や父母にまじって、出演する子ども達と同じ年齢のインディオの子ども達が、ハダシで、ボロをまとい、オドオドした動作で好奇心に輝く目で、大人の
すき間から食い入るように舞台を見つめている。
同じ年齢の子どもなのに、この貧富の差は胸をつく。
テレビでは「学校はあなたの近くにある」「学校はあなたを待っている」と学校に来るように呼びかけているが、貧しくて行けないのだ。
「あー絵を教えてあげたい」と思った。この子ども連の足元に咲いている草花を、頭上に広がる空の描き方を教えてあげたい。そのためには、画用紙も、絵の具も、筆も必要だ。それらは、この国ではとても高価。そればかりでなく、近くに売ってはいない。
野外劇が終り、教会の角では、慈善団体による、クリスマスのお祝いの果物酒"ゴンチェ"がふるまわれた。
観光客が、キャーキャー言いながら集まる。「わたしにも」「わたしにも」いろいろな国の言葉が大声で飛び交う。
その中に、インディオの子どもらもオズオズと集まる。彼らは、ほんとうに空腹なのだ。「わたしにも下さい」と言えず、どんどん後回しにされる。
あの時に、出会った子ども達のような子が、アリシア・ベカの映画教室−質素な道具、板のカメラ、リアカーの移動車−の授業をうけながら、堂々と自分の夢を語れる子になっていく。
私のメキシコでの切ない思い出とダブリ、涙なしには見られなかった。

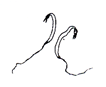
○私の教え子は
今年のアートスクールに来ているR君は、定時制高校に通っている。栄養に満ちた、ふくよかな体。
教室に入ってくるなり
「あー疲れたー」と連発する。
「三原色と自で、自分の見えるモヤシの根っこの色を作ろう」と、私が言うと「できない」と言う。
「できないんじゃなくて、やってないの」と私が言うと、教室の隅にいる三年先撃のM子さんが「ワッハハハハー」と教室中にひびく明るく大きく笑う。
しかし彼は「疲れた、もうダメダ」と言って、ドデ〜ンと座っているだけだ。
「三原色と白で、モヤシの根っこの色を作るの」と又言うと、あっという間に、適当に混ぜ合わせた色で、画用紙いっぱい棒を描く。モヤシの根っこのつもりらしい。そして「できた!キミ子さ−ん、できましたよ−」と大声をあげる。
「えっこの色でいいの?」とカマかけて間くと「いいの、できました」と言う。 私はモヤシの根のすぐそばに、彼の作った色をおき、 「この色とこのモヤシの根の色と同じ?」と聞く。(同じと言ってくれたら、ケリがつくと思いながら)
「あっちがう」と彼は言うのだ。〈ほんとうは、ちやんとわかっているんだ。ただ、めんどうなだけだ〉
「だったら、もう一度つくる。モヤシの根の色を」と私が言うと
「エ−イヤダヨ、疲れるよ。デキナイデスヨー」
私は新しい画用紙を渡す。
彼は又、デタラメな色のまま、画用紙一杯に線を描く。そして明るく大きな声で 「キミ子さ−ん、できました!」と大声をあげる。同じことをくりかえして、四,五回。
「もう、しつこいな。あたらしい画用紙いりませんよ」
「できるまで、こだわるわよ私」「色ができたら私を呼んで。根っこの描き方説明するから」と言ってもデタラメな色ですぐ描いてしまう。そして「デキター」だ。
「デタラメな色で、デタラメやっちゃって、ちっともデキテないじゃないの。デタラメならやらないほうかいい」「ワッパハハハ・・・」M子さんの笑い声がひびく。
「デタラメじゃないですよ」彼の言葉はあくまでも紳士的。 「じゃあ、この色とこの色は同じ?」 「いや、ちがう」と、ちゃんと答える。
「目の前のことをやらず、何が来週の課題?」とカッとして大声になると、又もや教室の隅から「ワッハハハハー」と楽しそうな笑い声。M子さんだ。
彼の感想文は空白がない。文字らしきものが、びっしりうまっているが、何を書いてあるのかわからない。
「キミ子さん愛しています。結婚してください」だけ読める。〈でたらめでいいから、適当に空白いっぱい描く(書く)〉〈「できた!」「わかってます」と大声をあげる〉〈明るく、ニコニコとふるまう〉それらは、彼が学習してきた九年間の学校教育の成果だ。
私は今、それと戦っている。
私には、アグエロ監督のやさしい声が聞こえるようだ。
「キミ子、どうして絵を教えるの?」
「彼らは、経済的理由ではなく、知的障書という名の差別を受け、人格も保証されていなくて、バカなふりをさせられている。だから、創造性を発揮できなくなっているの」
私はアリシアの声で一人つぷやく。