「バルセロナ」と聞くだけで、私の胸はうづく。青春時代(?)、笑いころげて歩いたランブラス通り。
そんな日々がよみがえる。
スイス人もアフリカ人もスエーデン人もイスラエル人も、みんな友達。男も女も、年齢様々。お互いに「フオルヘ」「キミコ」「マリ」と名前を呼び合った日々。先生さえ「マウ」「マリア」と名前で呼ぶ。
「先生には尊敬語を使うのは文法的に正しくない。」担任のガルバニーは言う。「学び合うもの同志は平等だ。だから先生と生徒は平等だ」私はすぐに納得した。
「反対!先生には尊敬語を!!」と叫んだのは、日本人の「シゲミ」とイスラエル人の「モンシュ」。
私は37歳だった。
|
 |
35歳の時「キミ子方式」のかなりの部分をまとめた。私は出会う人には必ず説明した。
「今までの絵の描き方<構図をとって、形を描いて、それから色を塗る>この描き方が絵を描けなくさせていたのよ。その逆にすればいいのよ」
ほとんどの人は賛成してくれた。
病院で出会う人たち。順番待ちの隣の席の人。電車に乗り合わせた隣の人。学校で出会う用務員さん。わが家に車を売りにきたセールスマン。ガスのメーターをはかりに来る人。喫茶店のマスターや客。宗教を勧誘する人。学校で出会う生徒さんたち。
私は公開授業をし、36歳の時に、授業記録をまとめ、あちこちの教育関係者の有名人に、その冊子を送った。
日教組という、学校の先生の組合の教育研修会にも出かけて発表した。 美術教育を進める会というところにも発表した。そこでの反応は、無反応。今の言葉で言えば「シカト」されたのだった。
<すごいことをまとめた>という私の自信は「こんな、わからずやばかりの日本に居ることはない。今こそ広い世界、外国へ行こう」と決意させた。
その当時、子供は小六、来年小学校一年、二歳だった。夫は少し前に、インド、ネパールを半年ほど旅して帰ってきていた。
「旅をしないと、いい女になれない。今度は僕が留守番するから行っておいで」と好意的。子供には「大学四年で妊娠して、小どもを産んだので、最後の一年間、思い切って勉強できなかったから、一年間思いっきり、自分のためにだけ時間を使いたいのよ」と言って納得してもらった。
|
さて外国、どこの国にしよう?
私が37歳の時、大学のクラスメート達はフランスやイタリア留学から帰ってきていたので、それらの国はもう新鮮ではなかった。
スペインにしよう。あこがれているガウデイの建築物を見に行こう。
ガウデイの作品といえば、大学を出て住んだ東京都日野市を思い出す。
当時、その街では前川恒男さんをリーダーに市民のための図書館づくりが行われていた。一人四冊、二週間。誰でも本が借りられる。
忘れもしない、初めて借りた本がガウデイの作品だった。それを見たときのショック。「わが家をガウデイのような家にしよう。ビール瓶やら、こわれた皿やらを壁にベタベタはりつければいいんだ」
うまいぐあいに、一九六五年あたりは、高度経済成長期で「古いものはダメなもの、新しいものはいいもの」という常識がはやった。
古いものはどんどん捨てられ、新しい製品がどんどんでてきた。
私たちは、中古のトラックを買った。初めて買ったのはスバルのバンが二万円で、床に穴があいているような車だった。次がハイエースというニッサンの中古トラック。その中古トラックは大活躍した。
「どこそこに、レンガが捨てられている」「あそこにソファが捨てられてある」という情報が入ると、すぐトラックごとすっとんで行けたからだ。
かくしてわが家は、ベニヤ板二枚分の大テーブルと、白樺の木のベンチと、焼き物をやっている友人の失敗作を引き取り・・・と、いつの間にかガウデイ風レンガ作りのみごとな手作りの家が完成した。
「わたしの部屋」という雑誌や、テレビ局が、取材に来た。テレビ局でわが家が画面に写し出されたら、そこにいたテレビ局のスタッフが「これ日本なの?いい家だなぁ」と見入っていたのを覚えている。
|
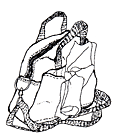 |
 |
一九七七年、ついにスペインのバルセロナに行く。
「ガウデイのほんものの作品群が見たい!」
毎日学校帰りに、ガウデイの作品を一つ見てから下宿に帰る。それを日課にしていた。
ガウデイの作品(建築物)は、今も使われているところが多く、「日本からガウデイに憧れてスペインに来た」というと、どの人も親切にしてくれた。そこで又、知人友人ができるのだった。
下宿の女主人も、私がガウデイが好きだというと「スペインの建築家たち」という本を読みだしたりした。
一九七七年は、スペインで初めて女性に選挙権があたえられた年であった。
デンマーク人のフオルヘは新聞記者で、どうやらスペイン初めての女性参加の選挙を取材に来ているようだった。
担任のガルバニー、37歳。新聞記者のフオルヘも37歳、私も37歳。クラスメートはそれ以下15歳のスイス人13人だ。
初めての女性参加の選挙ということで、あちこちで女たちが意見を言いはじめた。スペイン初めての地下鉄ストライキというのもあった。機関銃を持つ兵士が立って見張っている。
労働者は市民に対して演説している。「私たちの給料は安くて・・・」「安いっていったいいくらなんだい。なぜ、ストをして住民を困らせるんだ?」と市民が質問する。
私はその群衆の討論からスペイン語を学ぼうとする。
|
初めてバルセロナに行った時、出会うスペインの女性は<ピカソの描く女の人のように美しい>とまぶしいものを見るように見上げていた。でも何カ月か過ぎると、ピカソの描くような美しい人はいない。ピカソの絵は、理想の女たちだとわかる。
でも、女たちは生き生きしていた。選挙の時、誰を選ぶかで、嫁と姑がケンカして姑さんが出ていった下宿もある。
私の下宿では、毎月一回「夕ご飯は一人で食べてね。今夜は大事な会議があるから」とセニョーラはいった。
そして、この家にはペットの犬さえ入れない、いつも扉の閉じた部屋があった。その部屋へ、どこからともなくひっそりした感じで人が集まってくるのだった。
その部屋をのぞきたい。しかし、いつもしっかりカギがかかっている。
ところがある日カギが開いていた。おそるおそるのぞいた部屋は、上から下まで本がギッシリ、真ん中に八人くらい座れるテーブルがあり、テーブルの下まで本がギッシリ。
スペイン戦争で亡くなったご主人の書斎だったのだ。そして、その部屋に集まる人は、当時禁止されていたカタラン語で語りあっていたようだ。
ある日、下宿のカニョーラが「カタラン語の音楽会のチケットがあるけど行く?」と誘ってくれた。カタラン語の詩の朗読、歌、演奏だった。
「カタラン語だけどわかる?」と誰でもがやさしく声をかけてくれた。
私の通った語学学校は、バルセロナ大学の近くにあった。
昼休みによく大学近くの本屋に遊びに行った。広くて天井の高い本屋さんには、背の高い脚立がいくつもある。面白いのは、その脚立の上に座り込んで、ずーっと本を読みつづけている人たちがいるのだった。
私が「星の王子さま」のスペイン語の本だと思って買おうと、レジにお金を差し出すと
「これは、カタラン語の本だけど大丈夫?スペイン語の本もあるけど」と教えてくれるのだった。
モンジュクの丘にはミロ美術館がある。その美術館でミロの作品を見て出口へ向かおうとすると、そーっと誰かが、私の手にビラを渡す。
ミロ美術館の地下で、「カタラン語の講演会」をやっていたのだった。残念ながらカタラン語はわからないので参加できなかった。
|
 |
 |
二、三ケ月バルセロナに住むと「何の勉強をしているの?」と聞かれて「スペイン語」と答えると叱られた。「カタラン語こそ私たちの言語だ」「あなたの習っているのはマドリード語だ。クソ」というぐあいに。
当時はカタラン語は、学校で学ぶのを禁止されていた。しかし、確実に引き継がれていたのだ。
二年前のバルセロナオリンピック。私の家にはテレビがないので、オリンピックは仕事先のホテルに泊まった時に見た。閉会式だった。その放送を見て、思わず胸が熱くなった。
まずはじめに流れた閉会の挨拶がカタラン語だったからだ。次いでスペイン語、そして英語だった。そうか、カタラン語が公用語として堂々と話せる時代になったのか。一九七七年から17年が過ぎたのだ。
その時にスペインで出会った友人たちが「キミコ、あなたは大発明したんだよ。逆に考えるなんて、東洋人のあなただからできたことだよ。そんな大発見しているのに、こんなところでウロウロしてはいけないよ。日本に帰って、本を書きなさい。忘れちゃいけないよ。日本語の本は本とはいわないよ。英語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、最低五カ国語にしないと本とはいわないんだよ」とはげましてくれた。
酔っぱらい風のおじさんに、カタロニア広場で、キミ子方式の話しをしたら「あなたは哲学者か?」と尊敬してくれた。
あぁ懐かしいスペイン。私を生き返らせてくれたバルセロナ。バルセロナ大学の学生さんがデモをしていて、その時のスローガンが「すべての子ども達を学校へ」だったけど、あの頃、六割の子ども達は学校へ行けず、女の子はお手伝い。男の子は小間使いで働いていたが、選挙制が出来、新生スペインになり、オリンピックのできるスペインになったから、きっと、すべての子どもが学校へ入れる時代になったことでしょう。
今年12月、スペイン<バルセロナ・パリ>ツアーを企画しました。ご一緒しませんか? |
TOPへ
|