北海道の九月は、夕方からカーデイガンが必要だ。
中学三年生の秋のことだった。母が私に真っ赤な色のカーデイガンを買ってくれた。
色も、肌ざわりも、形も、ステキで色黒の私にピッタリ似合った。
私は、絵がうまい少女といわれていた。学校代表で、美術コンクールに参加した。
そのコンクールは、会場で、決められたモチーフを一日がかりで描く。今の美術大学の入学試験のようなものだった。
書道と、音楽もあったようだ。私の学校からは、水彩画の私と、ピアノのNさんが代表だった。
ピアノがひけるNさんは、東京からの転校生だった。言葉も洋服も物腰も、私の住む炭鉱町の人たちとは違って、上品だった。
毎週日曜に、北海道一の大都市、札幌までピアノを習いに行っていた。
私とNさんは、美術の先生につれられて、会場のある「深川」という駅に降りた。私の知っている町では一番大きな町だ。
商店街が駅前からズラーと並び、「〇〇を買うなら◇◇商店で・・」と、あちこちのスピーカーから店の宣伝が湧いていた。
大都会は、人も、多く、音もうるさく、私はカチカチに緊張していた。先生が駅前の食堂に誘ってくれた。そしてコーヒーを三つ注文した。コーヒー皿の上にスプーンがついている。私は一瞬ためらったものの前かがみになり、スープを飲むように、コーヒーをスプーンですすり飲んだ。
先生とピアノ代表のNさんは、カップを持って、堂々と前方を見て、口へ運ぶ。
そうするものだったのか!顔から火が出るように恥ずかしく、にがいコーヒーが、ますますにがかった。
|
 |
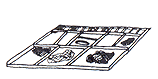 |
将来を見据えて
コンクールの会場では、人物画が課題だった。私はエイツと冒険したかった。そこで、白い絵の具で下地をぬった。そうしたら、いくら上から他の絵の具をのせても、下から白い絵の具がでてきて、うまく描けなかった。完全に失敗である。コンクールが終って、美術の先生は"野獣派"─マチス、ドラマンク、ドランなどが代表的な作家─の話しをしてくれた。
「それまでの美術の伝統を無視して、強い色を使ったり、予期せぬモチーフを描いたので、まるで野獣といわれた。美術史で印象派の次に出てきたグループなのだけど・・・」
私の、白い絵の具をつかった冒険を、なぐさめているのが、よくわかった。でも、やりたかった冒険で、それが失敗だったことは明らかだ。
最優秀賞はとれなかったけれど、次点の賞はもらったのだと思う。
後日、賞状と賞品が送られてきた。賞品は、色紙の絵だった。その絵を「有名な画家が描いたのだから大事にしろ」と担任の先生は渡してくれた。
その絵は、まるで私を描いたかのように、赤いカーデイガンと紺色のスカートの少女の坐像だった。
ずっと部屋に貼っていた。「将来は画家になりたい」と思いつめて、眺めていた。そして、私はますます、赤いカーデイガンがお気に入りになった。
|
高校に入った。
当時は女の子60人中4人しか高校に進学しなかった。
高校の制服は白い太い線一本はいったセーラー服だった。
ある寒い日だった。風邪気味の私は、制服の上に、自慢のカーデイガンを羽織って学校に行った。電車に乗って一時間、歩いて20分。
ポプラ並木が、まだ植えて六年目くらいで小さい。寒風がふきすさぶ雨竜平野のまっただなかの学校だ。
その朝、校庭で朝礼があった。朝礼の時、カーデイガンを脱ぐつもりだったが、とても寒かったので、そのまま朝礼に並んだ。
朝礼の後、家庭科の先生に「職員室に来るように」と言われた。
職員室に入るや「それは何ですか?」と、私の大好きなカーデイガンを、きたないものを見つめる目付きで蔑視した。 そして、「そんなものを着るなんて1」と言った。
母がくれた、大事な大事なカーデイガンをそんなものと軽蔑するなんて、悲しくて、なさけなくて、 ヘタヘタと床にくずれそうになった。
その女教師が、どうして私がカーデイガンを着ただけで、そんな憎らしそうな顔になるのか。まるで私が犯罪者だ。
「風邪をひいても、制服を守れ」と言っているのだろうか。
私はこの人を信用しない。私がもっとも大事にしているものを軽蔑したからだ。
その年の冬、高校の文芸部の冊子の表紙絵をたのまれた。私はためらいもなく、真っ赤な表紙に、ポプラ一本を黒で描いた。
|
 |
大事な<もの>
先日、ニュージーランドの映画作家の「ピアノレッスン」とい映画を見た。
命の次に大事なピアノ を、重くて運べないからと、海に置き去りにされたピアノをめぐっての物語だ。
私にも、誰にでも、もっとも大事な<もの>があり、その大事なものを犯してはならない。
私はフト「ピアノ」という映画を見ながら、私にとっての「ピアノ」は何だったろうかと思って、フト赤いカーデイガンを思いだした。
<もの>は単なるものでなく、様々な人との間をかいくぐった、人間との関係の<もの>なのだ。
浪人していた二年間、そして大学に通った四年間、そのカーデイガンを愛用した。
ヒジがぬけても、しゃんと形がくずれず、肌ざわりも相変わらず感じがよかった。
ついに、半袖にして、私の長男が生まれた時に着せた。私に似た色黒の赤ん坊に赤いカーデイガンは、とてもチャーミングだった。そして、次男のズボンにリフォームした。
赤いセーターがお店に売っていたり、誰かが着ていたりすると、他のどの色よりも、キツと見つめてしまう。そして手に入れたくなる。
あの昔と同じ色を、同じ材質のものをと、こだわってしまうからだ。でも、今だに二度と手に入ることはできない。しかし、あきらめていない。
あの高校生の時、私が先生だったら何と言ったのだろうか。
「すてきなカーデイガンね。寒かったからカーデイガンが必要かもしれないけど、制服が決まっているので守ろうね」と言うか、などと一人言を言って、時々なぐさめている。
母からもらったプレゼントで一番気に入っているのは、 赤いカーデイガンだ。
母が生きていれば84才くらいだという。先日、母の妹が、大阪であった私の講演会に来てくれて、そう言った。母が死んだ年齢に、あと四年。 |
|
TOPへ
|