Y君という青年が、アートスクールの生徒になった。
彼はB服装学院の学生である。「スタイル画が描けないので、何とかしてほしい」ということだった。
キミ子方式は、モノを、そのモノらしく描くことを主眼にしているので「スタイル画?」と驚いた。
彼は「いろいろなところに習いに行ったんですけど、ちっとも描けないんです」と言う。その真剣な目に、何とか答えたい思った。
まず、モノを見るテクニックを学ぶこと。一点から隣へ隣へ描き進める技術をと、キミ子方式の基礎のテーマを4つ描いてもらうことにした。そして、スタイル画も人間の動きを描くわけだから、人間の動きの心棒が描けなければ、どんなに激しく動くポーズもサマにならない。教室でも題材としてとりあげる、あの黄色いチョークを使って描く、滝口泰正さんの考えた「おだんご一つ、さくらんぼ・・・」と歌いながら描く方法で、どんな動く人も描けるようにしてあげたいと思った。
「おだんご一つ」と腰を描いて、「さくらんぼ」と背骨を描く、そして「おだんご二つ」と体を描くのではなく、ファッションモデルは八頭身か十二頭身くらいの方がスマートなので「おだんご五つ」くらいにしてはどうかと提案した。
どうして、デザイナー志望の彼が、キミ子方式を探し求めてきたのか、とても興味のあることだった。
彼は言う。「清水真砂子さんの『子どもの本のまなざし』という本を読んで来たんです」
「エッ?」。あの本は、子どもの本の作家達について書いたもので、私のことは一行か二行くらいしか書いていないはずだ。
|
 |
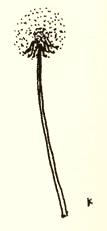 |
一人の青年を行動に駆り立てたその文章を、もう一度確かめたくて、私は清水真砂子さんの本を久々に取り出して読み直した。偶然にも、私はその時、カニグスバークの『ジョコンダ婦人の肖像』を読んでいた時だった。昨年末のイタリアスケッチツアーを思い出して読みたくなった本だ。
清水さんは、カニグスバーグの作品を論じている中に
「・・・その(カニグスバーグ)面白さが、なんの面白さであったかが、今ようやく私にも見えてきた感じがする。
カニグスバーグは「人生の真実」など語らなかった。イデオロギーからも意識的には遠かった。彼女には技術こそせっぱつまった要請と受けとめられていたのだ。
美術教育の松本キミ子はいう。「キミ子方式は技術である。〈素朴な心〉だけで絵をかかせたら、ほとんどの人は絵がきらいになる(松本キミ子著『絵を描くということは』(仮説社・一六七頁))
美術の世界で松本キミ子が批判されていることは想像に難しくない。だが、私は松本が「キミ子方式は技術である」と、あえていいきるまでに重ねてきたであろう否定のぼう大さを想う。「〈素朴な心〉だけで絵を描かせてきたら、ほとんどの人は絵がきらいになる。」は、そのまま日々を生きることにもあてはまるだろう。カニグスバーグは世間に流布する既成の多くの「物語」が子どもたちを、なにより自分自身を生きにくくしていること、そしてまた、作家たちが彼らの書く作品の中で、どんなにすばらしいモラルを語り、思想を語っても、それでもって子どもたちが目の前の日々を生きのびられるわけではないこと、人にはむしろそのためにかえって生きていくのがおっくうになることを、ずっと感じていたにちがいない。そこに求められていたのは技術だった。そんなのは何も新しいことではない。生活者なら誰でも考えることだ。」
|
私も彼のように、本の中の、たった一行(一つのセリフ)に感動して、著者を訪ねたことがある。その著者の名は板倉聖宣さん。
佐藤忠男の『学校の外から考える』(昌平社)の中に、佐藤忠男と板倉聖宣さんの対談があった。その中で板倉さんは
「ものを見るということは、よく見なさいといっても見えないのです。仮説をたてなければ見えてこないのです」というような意味のことを言っていた。
私はその一行に「わかった!」と声をあげた。
それまで私は〈描き始めの一点を教え、となりとなりと描いていくだけで、なぜ、生徒たちは絵がかけていくのか〉の理由がわからなかった。でも、その一行を読んで〈これは仮説をたてた〉ということだったとわかった。
その時に板倉さんの名前を大事なノートにメモをした。そして、その人の本を読みたい、できれば会って直接、話を聞いてもらおうと思った。
思っていると出会えるもので、それから、ほどなくして、勤務していた中学校の職員室の机の上に、板倉聖宣氏の講演会のビラが配られた。その時の驚きといったら・・・。
「どうして、この人を知っているの? 私が探し求めていた人なのよ」と興奮してさけぶ私に、ビラ配りの本人はポカンとしていた。彼は板倉さんのことを知らずに、ただビラを配っていただけだったのだ。
「講演会に行きましょう! この人スゴイ人なんですよ!」と、わたしの興奮はつづいていた。
わたしは誰よりも早く講演会場である日野市の小学校の教室に行き「なんで、このすばらしい人を迎えるのに、講演の参加者が少ないの? もったいない」と一人で怒っていた。
三人くらい講演を聞く人が集まったところへ御本人が現れた。
私は私の頭の中に、あざやかに記憶している顔写真そっくりな人が、教室に入ってこられた時に「板倉さん! 私は美術であなたと同じことを考えているんです。」とつめよった。板倉さんは困った顔をされて「僕、美術のことはわかりませんから」と、身体をのけぞって否定した。
〈そんなはずはない。私は、あなたと同じことを考えている。私は長い間、あなたを探していたのだ〉とつぶやきながら、一番前の真ん中の席に座って、一言だって聞き漏らすまいと講演に耳をかたむけた。
板倉さんの話は同感同感。私の反応に、板倉さんは少し意識してくれたようだった。
当時、私は三十六歳だった。子育ての真っ最中。六時までに子どもを保育園に迎えに行かなければならなかったので、講演の途中で席を立った。後ろ髪を引かれる思いだった。夕食の買い物用に持っていたサイフには二千円ちょっとしかなく、ありったけのお金で彼の本を買った。興奮していたので、空のサイフを本の売場に忘れてきてしまった。
その本売りに来ていた人が、六年後に私の本『絵のかけない子は私の教師』を出版してくれることになった仮説社の人だとは、その時にはもちろん全く知らなかった。
|
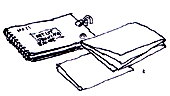 |
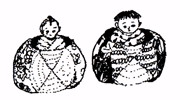 |
私はそのデザイナー志望の彼に
「教えてあげられるのは、モノの見方の技術だけなんです。絵が描ける技術だけ」と、そして、哲学者の三木 清の話をした。
彼は多摩美術大学の哲学の教授をしていたことがあるのだそうだ。その教え子で、今は絵本作家の方(名前を忘れてしまってごめんなさい)が
「三木 清の哲学の授業のほとんどは覚えてないのですが、ただ一つだけ覚えていることがある。『恋愛は技術だよ』と言ったことだけだ」と、何かの雑誌に書いてあったことを伝えた。
とつぜん彼は、私を正面から見据えて
「そうですよね、恋愛も技術ですよね」としっかり言った。
ところで、その若者のことを清水真砂子さんへ手紙を書いたら、彼女から返事がきた。
「・・・それにしても、私の本からキミ子さんの門の扉をたたくなんて面白い人がいるものですね。読んでくれたんだって、うれしくなりました・・・」
・ ・
この文を書き終えて、そういえば清水真砂子さんも、新聞紙上で書いた彼女の文章を読んで私は感激し、追いかけつづけ、つかまえた人だったのを思い出した。
|
このページのTOPへ
|